いつか帰るところ
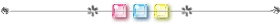
「ジタン?」
そこへ軽い足音とともに、聞き覚えのある明るい少年の声がしてきた。
「そうよ、さっき目が覚めたの。ちょうど良かったわね」
「ビビ、久しぶり」
まるで街へ出かけて会った友人に挨拶するような、彼らしい気軽な口調でジタンはビビに笑いかけた。
ビビは力が抜けたのか、へたりとその場に座り込んでしまった。
「よかった、ジタンおにいちゃんの目が覚めて」
「ビビはあなたが運び込まれてから、私と一緒にずっと看病していたのよ」
「そうだ、お姉ちゃんに伝えなくちゃ。お姉ちゃんには、ジタンがここに居ることも伝えてないんだ」
「あいつには…言わないでくれ」
「彼女に…ダガーに伝えないくていいの?」
「ボクも思うよ。お姉ちゃん、すごく悲しんでいたんだよ」
ジタンは一呼吸置いてから、はっきりとした口調で言い切った。
「あいつには言わないでくれ」
「どうして?彼女のことが大切なんでしょう。あの人もあなたのことをずっと心配しているのよ」
「今のオレの姿を見て、あいつがどう思うか?」
確かに今のジタンの状態は良いとはいえなかった。イーファ樹の石化が日に日に体をむしばんでいき、もう足先と手先は動くこともないぐらい固まっていく。魔の森のように一度に石化するのではなく、じわじわとやってくる石化の痛みに耐えなければならないし、白銀の針はほとんど効果がない。
見込みがないといっても過言ではないのかもしれない。
「半年近くもダガーのことをほおっておいた奴で、いつ死んだっておかしくないやつをさ」
「…」
「やっと落ち着いてきた頃なのに、この姿を見たらまた悲しむよ…あいつは」
「治るまで、絶対に会わないの」
「…あぁ」
それからの生活は楽しかったといえるだろう。石化が進行していって歩きづらくなったジタンのところへ、いつもビビが来てくれたのだ。
ジタンは、黒魔導士の村から少し離れた景色の綺麗な場所に看病されていた。それは、ビビの住んでいる家のすぐ側に建てられている。そこで、ビビは毎日村のいろいろなことを教えに来てくれたり、冒険中のことを話していたのだ。そして、ある日ビビは数個の人形を連れてきた。ビビそっくりの容姿の人形を。
「ビビ、これ何に使うんだ?」
その人形を目を皿のようにして見つめながらジタンは尋ねた。
「かれらはボクの子供達なんだ」
「ミコトのお姉ちゃんが作ってくれたんだ。でも、この子達は戦争にだなんて絶対に使われない。この子たちにはボク達の記憶を預けるんだ。ボクがみんなと冒険に出かけたことを教えてあげるんだよ」
「ボクもいつかは止まってしまうよ。だけど、この子達に伝えた記憶だけはずっと残っていくから、ボクは悲しくないよ」
そう言ったビビの笑顔には、せまりくる”止まるとき”への恐怖とか悲しみなどは一切なく、ただ純粋に希望の色が広がっていた。
だが、その日を境にビビの足はジタンのところへ向かうことはなくなった。
それからも、石化はどんどん進行していった。ミコトはテラの医学も使い、なんとか治そうと手を尽くしたが、もう他に手はなく、後はジタンの生命力に頼るだけとなっていった。
そしてビビもまた、そのときが足音を立てて近づいてきていたのだから。
どんどん消えていく、色あせてくる記憶。
仲間と過ごした大切な、ずっと残しておきたいと心にしまっていた記憶。
それがボクから少しずつ消えていった。
いつも空を見上げて過ごすことが多くなっている。
動かしたくても体が言うことを聞いてくれなくて、
ボクも”止まる時”が来たのかな?
それでも彼らがいるから、ボクの記憶は消えないんだ。
その時はやってきた。
月が、とても綺麗な日だった。
手をのばせば本当に届きそうな気がする。重なった蒼い月と赤い月。暗闇に輝く姿はすごく綺麗だった。
でも、綺麗過ぎて悲しかった…。
今日は、あのときの仲間達が集まってきたらしい。さっき黒魔導士の村のほうから、いつもよりも多くの人声が聞こえた。
そのなかには、あいつもいるんだろう。別れてから半年以上経ってるんだ、少しは落ち着いてきただろうか?オレのこともさっぱり忘れてくれただろうか?
目を閉じると、不思議といつも以上にいろいろな音が聞こえてくる。静かな木々のざわめきや小川のせせらぎ。もう仲間達は眠っているのだろう。そのとき、軽く扉の開けられる音がして、呼びかけてみた。
「…ビビ…か?」
でも、そこにいたのは妹だった。ただ、いつものどこか大人びた静かな表情とは違い、明らかに動揺していて、声もうわずっている。
「ジタン……ビビが…ビビが…」
素朴な樹を主に建てられた家には、多くの人々が集まっていた。黒魔導士達やジェノムのみんな、そしてあのときの冒険をした仲間達。みんなが、口々にビビに声をかける。ビビは虚ろに瞳をあけながら、耳を傾けていた。そして、そっと語りだした。
「毎日、ジタンのことを話したんだよ……
ボクたちのとても大切なひとがいたって……
生きてることの大きさを教えてくれたひとだって……
生きるってことは、永遠の命を持つことじゃない……
そう教えてくれたよね?
助け合って生きていかなきゃ意味がないんだって……
別れることは決して悲しいことじゃないよね?
離れていても心が通じ合ったよね?
そんな大切なことを教えてくれたんだよね?
ボクが何をするために生まれてきたのか……
ボクがいったい何をしていきたかったのか……
そんなことを考える時間を与えてくれてありがとう
好きなことだけをやり続けるっていうのは
実はとても難しいことなんだよね……
みんな……とてもえらかったんだなって思ったよ……
孤独を感じた時にどうすればいいかなんて
それだけは教えてもらえなかった……
本当の答えを見つけることができるのは
きっと自分だけなのかもしれないね……
ボク、みんなとめぐり逢えて、とてもうれしかった……
ずっと一緒に冒険したかった……
だけど、別れる時は……必ず来るんだよね
みんな……
ありがとう……
さようなら……」
「ボクの記憶を空へあずけに行くよ……」
部屋の中は嗚咽の声やすすり泣きが響き、だれもが悲しみにつつまれた。そっと、ガーネットはエーコを抱きしめた。優しく髪をなぜて慰める。だが、泣きじゃくるエーコをぎゅっと抱きしめる姿は、自分が泣きだすのをこらえるかのようにも映った。
そして、外でも一人の少年が壁に寄りかかり崩れるようにその場に座り込んだ。不自由な体に無理をいいなんとかここまでやって来たのだ。その隣で涙を流す妹の肩をそっと抱きしめていた。
泣きつかれて眠ったエーコをソファーに寝かせると、音を立てないように立ち上がると外へと足を向けた。
いつも静かな黒魔導士の村も、いつにも増して静まり返っていた。
露に濡れた草花の間を通りながら、せせらぎを奏でる小川の側に腰を下ろし、膝を抱える。
ビビ…。
いつも一番頑張っていた少年。自分の生きる意味をずっと探していて、気弱だけどすごく強かった優しい子。私よりもずっと勇気があったわ。自分のことをきちんと見つめて、受け止めていたもの。そして、ジタンのことをずっと慕っていた。
そのとき、カサッという葉の揺れる音で振り返った。
そこにいたのは、ミコトだった。その姿に、つい彼の姿を重ねていた。こんなとき、彼だったらどうするのだろう?
「ビビは幸せだったわ。私はそう思うの」
ミコトが隣に腰を下ろす。
「あの子はいつもあなた達のことを話していたわ。私も一緒に冒険したかのように、あなた達のことをよく知っているつもりよ」
「あの子はあなた達と冒険したときが一番幸せだったといっていたわ。いつも明るくてみんなを助けてくれる、でも本当は少し寂しがりやだったジタンお兄ちゃんと、優しくて心があたたかいダガーのお姉ちゃん。強がりを言うけど優しいエーコ。見た目は少し怖そうに見えるけど、すごくいい人なサラマンダー。ずっと心から想う人を大切にしていたフライヤのお姉ちゃん。頼りがいのあるスタイナーのおじちゃん。1つのことをずっとやりとげようとする、意志の強いクイナ。みんな一生懸命に自分の生き方や自分自身を探していて、みんなとってもすごかったって。あなた達に会いたい、と言っていたわ」
涙が、止まらなかった。
ミコトが、私がエーコにしたようにそっと髪をなぜてくれた。泣き止むまでずっと。
彼女も変わったと思う。初めにあったときは、言葉がしゃべれたり意思を持つだけで、一切表情を見せなかった。でも、今は彼女も、頬に涙を流しながらビビのことを悲しんでいるのだ。
きっと、あの純粋な少年にふれて、彼女も変われたのだと思った。ビビは会った人をみんな幸せにしてくれるような、忘れかけていたような純粋な気持ちに気づかせてくれるような少年だから。
「ありがとう、ミコト。あなたもつらいのにごめんなさいね」
「もう大丈夫なのね。…あの、こんなときに聞くのも…だけど。ジタンに…会いたい?」
真直ぐに向けられた青い瞳は彼を想わせる輝きがあって、ごまかすこともできずそっとうなづいた。
「本当に…本当に大切なの、彼のことが」
口にした言葉は震えていて、消え入りそうな気がした。
「もう何ヶ月も会っていないのに?もしかしたらジタンはもう会えないかもしれないのに?」
「……会えないから大切じゃないなんていうのじゃないの。それに私は信じてる。絶対にジタンは生きているわ。もし私が彼のことを忘れてしまったら…ジタンはどうすればいいの。ジタンの居場所を私が持っていれば、いつか…」
「彼はきっと喜ぶわね。自分のことをここまで思ってくれている人がいるのだもの」
ミコトは微笑すると、立ち上がり私に手を伸ばしてきた。
「眠れないとは思うけど、少しは横になったほうが良いわ。行きましょう」
いつのことだっただろうか?
前にもこんな夜に、彼の差し出されて手に手を重ねた記憶があった。
もちろん彼の手に比べれば、ミコトの手のほうが小さくて細いけれど、でも向けられた微笑は彼にそっくりで、頬にひんやりとした雫の感触がした。泣かないようにしようと思ったのに…。
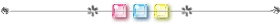
Next
Back
Novels
Index