いつか帰るところ
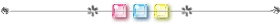
出来ることなら―――…少しでも側にいたかった。
今までの暑い寝苦しさがうそのようになり、涼しい風が流れるようになったある夜の日。 ジタンとの別れからもう半年が過ぎていた。
ガーネットは、外に開けた窓枠に腰かけながら布に包まれたものを大切そうに持っていた。白色の柔らかな布に包まれたそれは、空から降りそそぐ月の光を反射させていた。ガーネットはそれを壊れ物でも扱うかのように優しく抱えていた。涼しい風一陣がふわりと頬を撫ぜて通りすぎていった。
小さな声でガーネットは歌いはじめた。静まり返った闇夜の空気を小さく揺るがす。彼と自分の歌を――。その歌声は、暗い夜空に溶け込んでいく。
澄んだ綺麗な声な歌声は、誰の耳にも聴いていてとてもここちがよい歌声だが、どこか寂しく物悲しげだった。彼女は毎夜ごとにいつも欠かさずその歌を口ずさんでいた。甘くも哀しい調べは風を乗り継ぎ、今宵も切なげ響きわたった。ガーネットの護衛を務める奥宮の者たちは何度となくこの唄を耳にした。そのたびに穏やかな気持ちになりながらも、なぜ王宮の宝玉と呼ばれる女王がこのような哀しげな唄を歌うのかと疑問に思ったという。事情を知っている者たちは、この調べが誰のために歌い続けられているのかを知り心を痛める。
あの冒険から帰ってきて以来、よくガーネットはこの場所にいることが多いのだった。それは、イーファ樹に一番近い窓だからだ。
アレクサンドリアに帰ってから、慌しく時間がすぎていった。
本当は正式な王位継承者ではない、とガーネットが明かしたというのに女王に即位できたのは、アレクサンドリアが敗戦国となっていたことと、バハムートによってアレクサンドリアの町が壊滅的な状況になっていたためというのが最もな理由だ。王族の血縁の者もまるで押し付けるような形で王位をガーネットに渡したのだ。
そして、アレクサンドリアの復興が始まった。
建物を立て直したりと少しは直されていたが、アレクサンドリアはとても酷い状態だった。強盗や放火などがとても多く、街は荒れていた。バハムートの災害によって、家族が亡くなってしまった人も多くいたのだ。そういった人達のためにも、なによりも街を復興させるためにガーネットは力をそそぐことにした。
だが、即位したガーネットを助けてくれる貴族や大臣はとても少なかった。
大抵の貴族は、まず自分の土地と財産を守ることに専念していたのだ。
中には、ガーネットのことを幼い頃から見知っていて助けてくれる大臣や、アレクサンドリアのためにと手助けや援助をしてくれるものいたのだが、本当に数えるほどであった。
戦争を起こしたのはブラネとはいえ、他国からアレクサンドリアは賠償金を要求されていたのだ。ガーネットの父親とシド大公が親友で、ガーネットとも親しかったとしても、プルメシアのパック王子がフライヤたちからガーネットについていろいろ聞いていたとしても、一切関係ないのだ。
アレクサンドリアの財政は、ブラネが戦争に多くの資金を詰め込んだためとても貧困とした状態だったため、貴族たちは賠償のために国土を売ってしまうのかもしれない、と考えたのだ。その結果が自己の財産を守ることに繋がった。
アレクサンドリアは、霧の大陸では一番の領土を持ち、砂漠なども無く土地の豊かな国だったからだ。
しかし、自ら各国へ向かい針の筵のような状態で何度もガーネットは交渉し、土地を失うことなく、植民地になることもなく、一度では返せない賠償金を数年に分けて返せるようにしたのだ。そして、その資金のために国宝級の大切な宝まで売りはらって、国を立て直したのだ。
ガーネットは城下へもよく出かけ、国の人々を励ますこともよく行ったのだった。慈愛の微笑を浮かべて、城下のいたるところで短いけれど心のこもった演説をして、多くの人が深い悲しみを癒されていた。
そして、その姿に心打たれた貴族達がどんどんガーネットの味方になっていった。それから、驚くことに諸国も目を見張るようなはやさでアレクサンドリアは奇跡の復興を成し遂げたのだ。
半年たった今では、街並みも完全とは言えないがほとんど前のようになり、国民の生活もだんだん戻り始めてきた。
そうしたところで、やっとイーファ樹に検索隊を送ることができたのだ。
リンドブルムも協力して、石化したイーファ樹に通路を作るためのドリルも持ちこまれていた。
イーファ樹は酷い状態だった。テラとガイヤの融合のとき、イーファ樹は暴走し、今では完全に石化して中に入ることすらままならない。そこで、大きなドリルを使ってイーファ樹の根に穴を開け探索することになった。
しかし、探索隊が見たのは悲惨な光景だった。
「それで、これが今回の探索で見つかったものです。」
探索隊の指揮官が、布に包まれたそれをガーネットに手渡した。
見るのが怖かったが、ガーネットはそっと布をめくってみた。
それは、一振りの短剣だった。独特な形をしていて、刃の部分は薄い緑色の剣で、柄の部分には乾いてはいるが赤い血がついていた。それは、オリハルコンだった。
クジャを助けに行くとき、ジタンは盗賊刀では持ち運びに不便なため、扱いやすいオリハルコンを持ってでかけていた。
そして、柄の端の方に「Z」、そう彫られていた。
「……イーファ樹の内側に入ったときに見つけたものです。」
ガーネットは、唇をきゅっと結んでうつむきながら部屋を飛び出していった。
「ガーネット様!」
ベアトリクスが呼びとめても、ガーネットは振りかえらず私室に入ってしまった。
ドア越しにガーネットのすすり泣き声が聞こえてくる。ベアトリクスは、ドアにもたれかかり、目を閉じた。
いつも、人々に笑顔を振りまいて、人々の心を癒していた女王陛下。
でも、一人になると悲しげにイーファ樹のある方角を向いて泣いている女王陛下を誰が想像できただろうか。
あの戦乱に関わったものなら分かるかも知らないが、何も知らない人々から見れば、そんな風に泣いているところなど想像できないだろう。
どれだけ笑顔でいても、本当にガーネットが心から笑った日など一度も無かった。彼と別れてから…。
その日ガーネットは一度も部屋から出てこなかった。
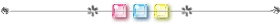
Next
Back
Novels
Index