いつか帰るところ
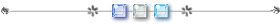
はっきりとはしない意識の中、ぼんやりといろいろなことが浮かび上がってきた。
かすかに覚えている、テラのこと。
もっとも自分がテラで過ごした時間はあまり多くない。ガイヤで過ごした時間の方が遥に多いのだから。そして、わずかばかりの寺で過ごした時間も物心つく前だったから、ほとんど何も覚えていないに等しかった。
ただ青い光が頭から離れなかった。
思えば、この青い光だけをたよりに旅をしたこともあった。故郷探す旅。
このテラにおいて青い光を見ない日は無かった。どこへいても、何をしていても、この光に見張られているような気がしていた。それが嫌だったのを漠然と覚えている。何がどう嫌だったのかは言い表せないが、ともかく嫌で嫌でたまらなかった。
そして、自分は記憶の彼方の地にいた。
顔色一つ変えないで、ぼんやりと青い光を見つめている、自分と似ている人達。茶色交じりの金髪に猫のような長い尾。ここは、ブラン・バルなのだろうか。この世界から生というものは感じられない。ただ、どこまでも続く静けさとまとわりつくような光だけがそこにはあった。
ふと、隣を見ると、とても小さな少年がいた。少年は一生懸命に無表情で青い光を見つめるジェノムに話しかけている。その少年は紛れもない自分であった。
―――オレ、何やっているんだろう。これは、夢?
周りを見ると、そこは間違いなくテラのブラン・バルだった。中央には、やはり青い光の湖があった。
黒魔道士の村に預けたはずの彼らがなぜここにいるのだろうか。いや、それよりも自分はどうしてここに、こいつは誰なんだろうか。疑問ばかりが先走りして、答えが追いついてこない。
すると、また闇に包まれた。
劇でよく使った暗転。そんな感じのイメージがした。光一筋すらなくて、自分の姿すら見ることができない。
再び光が大地を照らしたとき、そこはリンドブルムの劇場区だった。
劇を見に来る客や買い物を歩き回る人々、そんな見慣れた光景がそこにはあった。どこも何も壊れていない。ブラネ女王によって壊されたはずの市街が、そんな様子もなく立ち並んでいた。人々の表情にもそんなところは微塵も感じさせられない。自分はそのざわめく雑路の中に佇んでいた。
近くにもう見慣れたアジトがあった。自分が来る前からずっと時を刻み続ける大時計。一度も止まることのなかった姿がそこにはあった。そして、扉一枚隔てたアジトからは、明るくて楽しそうな声が響いていた。
近寄って窓から部屋を見てみると、そこにはまだ小さい自分の姿があった。まだ10か11歳ぐらいであろう。隣にいるブランクと何か言い争っている。
いつだったか小さな頃にパグーに拾われて、それからはずっとリンドブルムで過ごしてきた。そこで過ごした日々はよくブランクとケンカして、ボスにはたくさん怒られて…。難しい芝居の台本を渡されて戯曲と格闘したり、みんなで宝探しに出かけたり、ご飯作りに失敗したり。
毎日騒々しいぐらいだったけど、すごく楽しかった。
思い出すときり長いほどたくさんのことが鮮明に浮かび上がってきた。初めて劇の主役を演じたときのこととか、ちびタンタラスの汚名返上ために出かけたこととか。いろんな思い出がよみがえってくる。だけど、それよりも…何かつっかかることがある。
―――オレ、いままで何をしていたんだ。…クジャを助けに入ったんだ。でも、あいつが気を失って…そしたら、ツルが巻き付いて…。その中に、オレ達は閉じ込められたんだ。ツルの中のはずなのに、なんで…。
辺りは、夕方に変わっていた。茜差す空がどこか寂しかった。愁哀、この感情をそう呼ぶのだろうか。劇場区にたどりついたエアキャップから誰かが降りてきた。その脚はアジトへと向けられている。落陽の光を背に受けて、逆光で顔はよく分からない。だけど、すぐに分かった。
自分だ。
さっきよりも少し大きくなった感じだ。うつむきながら、アジトの扉の前までたどり着いた。しかし、扉は開けずにそのまま佇んでいた。
いつ頃のことなのか、よく分かった。あのときのことなのだ。
故郷が知りたかった。自分の両親はどんな人だったのかとか、どんな地に生まれたのだろうかとか。それらを見つけてどうするのかと問われても、答えはないだろう。どう頑張ったとしてもそのときに戻ることはできないのだから。だけど、それを自分は探していた。もしかすると、自分自身を集めていたのかもしれない。それらを探し出すことが自分にかけたものを取り戻しているように思えたから。
その結果、タンタラスを1人抜け出て「青い光」だけをたよりに探しに出かけた。青い光、それが何なのかは分からなかった。だけど、いろんな街を渡り歩けどば、きっとそこへ繋がっている。そう思った。
でも、探していた故郷はどこにもなかった。青い光は、どこを探しても見つからなかった。自分の故郷が見つからなくて、自分がどこの誰なのか分からなくて、…自分の居場所がなくなった気がしていた。
自分が最後に行きついた先は、アジトだった。何も言わずに飛び出してきて、今更のこのこ戻ろうなんて情けないと思った。でも、そんな情けない自分を迎えてくれる場所があった。
意を決して扉を開けると、奥の椅子にボスが座っていた。ただ、座っていた。自分を見ても何も言わず。気まずくて何も言えないでいると、ボコボコに殴られた。だけど、最後にはにこっりと笑って迎えてくれた。ボスなりの表現だったと思う。その後は、どこに行ってたのか、とか何も聞かないで、ただ今までと変わりないように接してくれた。それが嬉しかった。
―――死ぬ直前って、今までのこと思い出すって聞いたことあるな。もしかして、オレ死んだのか…?
また、辺りが真っ暗になっていった。本当に一面真っ暗で、その中に1人ぽつんといる状態だった。すると、後ろの方から声が聞こえた。
振り返ると、そこはリンドブルムの見張り塔だった。空が澄みきった青い空で、とても風が気持ちよかった。そして、そこには彼女がいた。澄み渡る背景の中で、真っ白なハトに包まれていた。
―――…ダガー
ダガーはいつものあの歌を、歌っていた。響きがとても綺麗で、快くて、澄みきっていた。空に溶け込むような歌声だった。今では懐かしい長い黒髪が背の辺りで止められていた。絹糸のように滑らかだ、と誰かが賛美していたのを覚えている。ダガーは歌をやめて、長い髪を揺らしながらゆっくりと振り返った。傍にいた、白いハト達が一斉に空へと飛び立っていった。あのときと、同じだった。狩猟祭の前に彼女の元へ脚を運んだときのことだった。
ダガーの側へ近寄ろうとすると、また周りが真っ暗になってダガーも消えてしまった。
しばらく、暗闇の中に包まれていると、優しい声が耳を撫ぜた。
「ジタンがわたしたちを守ってくれたように…守ってあげたいの…ジタンを」
徐々に辺りが明るくなり、自分がいる場所が分かってきたそこはパンデモニウム城だった。まがまがしい無骨な城。その中で自分は自分を見失っていた。もうどうでもよくなって、自分の存在がたまらなく嫌になって。そして、その部屋にはダガーとあの時のオレがいた。
心の傷というのは、そう簡単に治るものではないらしい。心にぽっかりと穴があいた感じでいつも血を流している。すごく、深い傷。心から血を流しながら、自分は助けを求めていたのだと思う。
あのとき、自分がテラの人物で、ガイアにとって死神としてつくられたと知ったとき、足元が崩れていくような感じだった。もしかしたら、自分自身の手でガイアを、仲間を、ダガーを壊してしまうかもしれなかったかと思うと、怖かった。ガイアの人間に迷惑なんてかけられない、そう思うと誰の言葉も耳に入らなかった…。
そんなとき、彼女の言葉がすごくあたたかくて、一生治ることがないと思っていた深い傷はその言葉で、傷跡もなく綺麗に治ったのだ。
―――彼女のためにも帰りたい…
泣き虫なお姫様だから、オレが側についていないと…。
それに、側にいてあげたい。
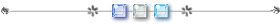
Next
Back
Novels
Index