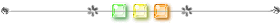いつか帰るところ
もう、会えなくなるかもしれない。
土の混じった乾いた空気が頬を撫ぜた。今も眼下ではまるで生き物のように根が暴れまわっている。大地をえぐる弦を見れば、中心地がどれだけ悲惨な事は火を見るよりも明らかだった。しかし、彼は言った。この暴れ狂うこの地にたった1人で兄を助けに行く、と。
それは、頭で考えるより心で行動する彼らしい答えだった。
彼の兄の行ったことは酷いことばかりであった。彼を見知らぬ土地に置き去りにし、彼をねたみ、憎み、殺そうとまでした兄。だけど、彼には分かっていたのだろう。兄は孤独だったことを。生きたいと願うのは人間の本能だ。だが、それが人の手によって簡単につくられたり消されたりするような中にあったら、誰だってどうしようもないようなやり場のない怒りに飲み込まれるのではないかと。それに、最後になって兄は間違いに気がついたのだ。そして弟とその仲間達を救おうとした。
彼はそんな兄を見捨てる様な気にはなれないのだろう。私の言葉も彼の決意の前には何の力も持たないことは分かっていた。
荒れ果てた荒野の中、私には彼の声だけが響いていた。周りには樹にあらされ削られていく大地の叫びや、風の嘆きもあっただろう。だけど、そんなものは一切耳に入らなかった。彼の声だけがこの世界にあるかのようにきこえた。彼の声が優しく耳を撫でる。
「ダガー―…… いや、王女様……」
彼が呼びかけたのは冒険の中で自由に生きてきたダガーではなく、至高の座に着く女王ガーネットへ向けたものだった。彼は片ひざをつき目上の者へ対する態度をとりながらうつむき加減に口にした。今まですぐ近くにいたはずの彼が遠ざかっていく気がした。急に大きな隔たりを感じて、彼の生きていく世界と自分の生きていく世界に壁が作られた。言いようのない孤独と寂しさ。
「あなた様を誘拐するお約束は残念ながらここまでです。……わたくしめの勝手をどうかお許し下さいませ。」
そして、女王のガーネットは答えた。慈愛の女王と称されるアレクサンドリアの宝玉として。
「いいえ……わたくしにはその申し出を断わる理由などありませんわ」
…うそつき。
女王のガーネットは心からのお礼を従者に述べるように、にこやかに振舞った。それは人々が口にする笑みを絶やさない慈愛女王。だけど、ただの少女のほうのダガーはどうすればいいいのだろうか。
女王のガーネットのほうはそれで賛辞の言葉を述べればいいのかもしれない。だけど、普通のダガーは?
女王としての威厳をもたなくてもいい、自分の気持ちを素直に打ち明けてもいいダガーのほうの私は、そんなすまして答えられるはずがない。行かないでほしい。ねぇ、ジタン。どうしたら側にいてくれるの。どうしたら、あなたの事をこんなにも思っていると伝えられるの。ダガーを無視して、女王のガーネットは言葉を続ける。
「それに、わたくしの方こそ、あなたにお礼をしなくてはなりません。あなたに誘拐していただかなければ、わたくしは自分ひとりでは何ひとつできない、つまらない人間のままだったでしょう。」
確かに私は彼のおかげで変われたの。
彼に会わなければ、私は王位という名のきらびやかに飾りたてられた籠の中の、外の世界を何一つ知らずさえずっている小鳥だったであろう。女王としてどうふる舞えば良いのか、そんなことばかり考えている。ただ、ただ虚しい世界で。
でも、ある日自分では開けられなかった籠の扉を開けてもらい、外の世界に飛び出していった。そこで得たものはかけがいのないもの。たとえ命を賭したとしても後悔しないぐらいの半身とも言うべき存在。たった一人だけの。
「でも、あなたと出会って、いろいろな世界をめぐり、いろいろな人々と出会い、いろいろなことを学ばせてもらいました。」
お城のお姫様だったら、あんな野原の大平原や、うっそうと茂る森、砂だらけの砂漠、誰も踏み入れたことのないような世界を歩くことも見ることもなかったであろう。
彼に会わなければ、ビビ、フライア、クイナ、エーコ、サラマンダー、タンタラスのみんな、黒魔導士の村のみんな、ジェノムのみんな、冒険の最中に出会った沢山の人々達にも会えなかったであろう。
そして、外の世界について何一つ知らない無知な自分に、彼はいろいろな事を教えてくれた―…。
「時には大変なこともありましたが、本当に大切なものがいったい何なのかを知ることができたように思います。これまでの長い旅の思い出は何物にも代え難い宝物になるでしょう。本当に…… 本当にありがとうございました。」
女王ガーネットは笑う。柔らかな笑顔で。寂しさのかけらもないように。
だけど、ダガーが叫んだ。…辛かった―…。
ここで別れたら、きっともう会えない。
でも…、彼らしさを失ってほしくはなかった。それを失えば彼は彼でなくなるし、きっとこのときのことを一生後悔して過ごすだろう。ずっと胸に重たい石を抱きながら。
だから…だから、泣かないようにしていたのだ。彼の後ろ髪をひくようなことはしたくなかった。
きっと私に役者は向いていない。そう思った。
ダガーは最後まで完璧にガーネットを演じられなかった。
「でも…… でも…… おねがい、必ず帰ってきて……。」
それは、女王でもなく、アレクサンドリアの政治者でもなく、1人のダガーとしての言葉だった。
帰ってきて―…。
もう泣きそうだった…。彼に背を向けて、彼に分からないように…。でも、声は涙声だった。
分かっていたのだから。どんな言葉も、どんな願いも、今の彼には通じない。彼は風のような人だから。自分の考えのままに生きる、海と空の蒼の中を飛び交うような人だから。
どうすればいいか、よく分からなかった。
ただ、今ここでアイツを助けに行かなかったら自分は一生後悔する。そう思ったから、助けに行きたかった。
そして、彼女はそんな自分の気持ちを本当に分かってくれているからこそ、引き止めないでくれたのだ。でも、本当はすごく辛いのだと思う。自分が彼女にしてあげられることは…。
帰ってくるよ、そっと彼女の目尻に浮かんだ涙をぬぐってあげた。
「笑ってくれないか?ダガーの笑顔が1番大好きだ。」
にこっと笑いかけると、彼女は、手の甲で目元をこすって、微笑みかけてくれた。彼女は、慈愛の姫君として、周りから噂されるほど微笑みを絶やさないのだ。でも、自分にかけてくれる微笑は、それらとはまた異なった優しい微笑だと思う。そんな飾らない笑顔が大好きだ。
たぶん、自分はもうこれで帰ってはこられないのかもしれない。この言葉は嘘になるかもしれない。それでも、この言葉が今1番彼女の聞きたがっている言葉だと思う。そして、自分も生きて彼女の元へ戻ってきたい。
可能性が幾ら低くても、口に出すことでそれは実体を伴うような気がした。そして、それは自分自身への確認のようでもあった。
必ず、また彼女の元へ戻ってくる。